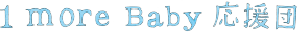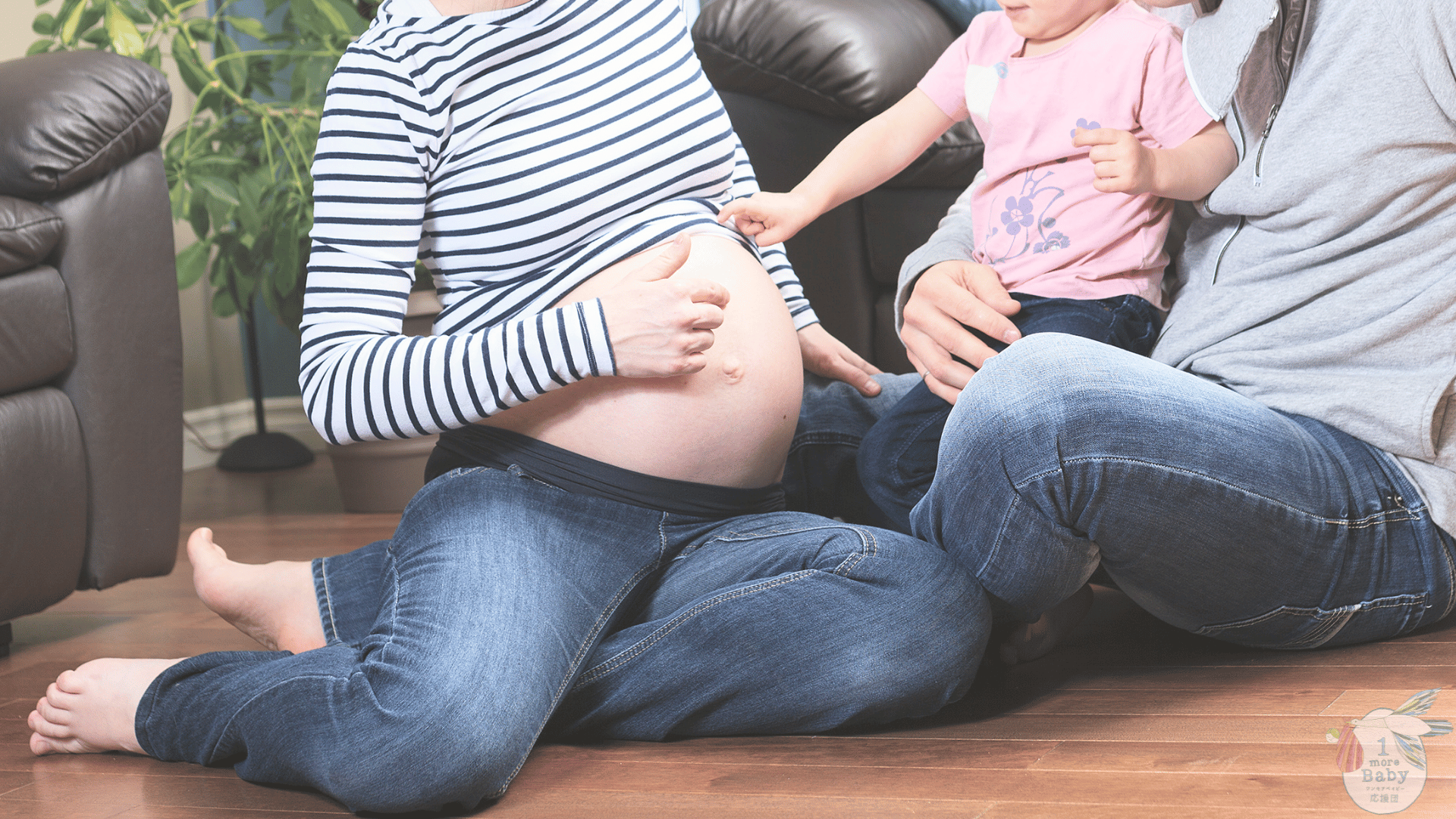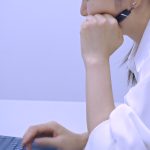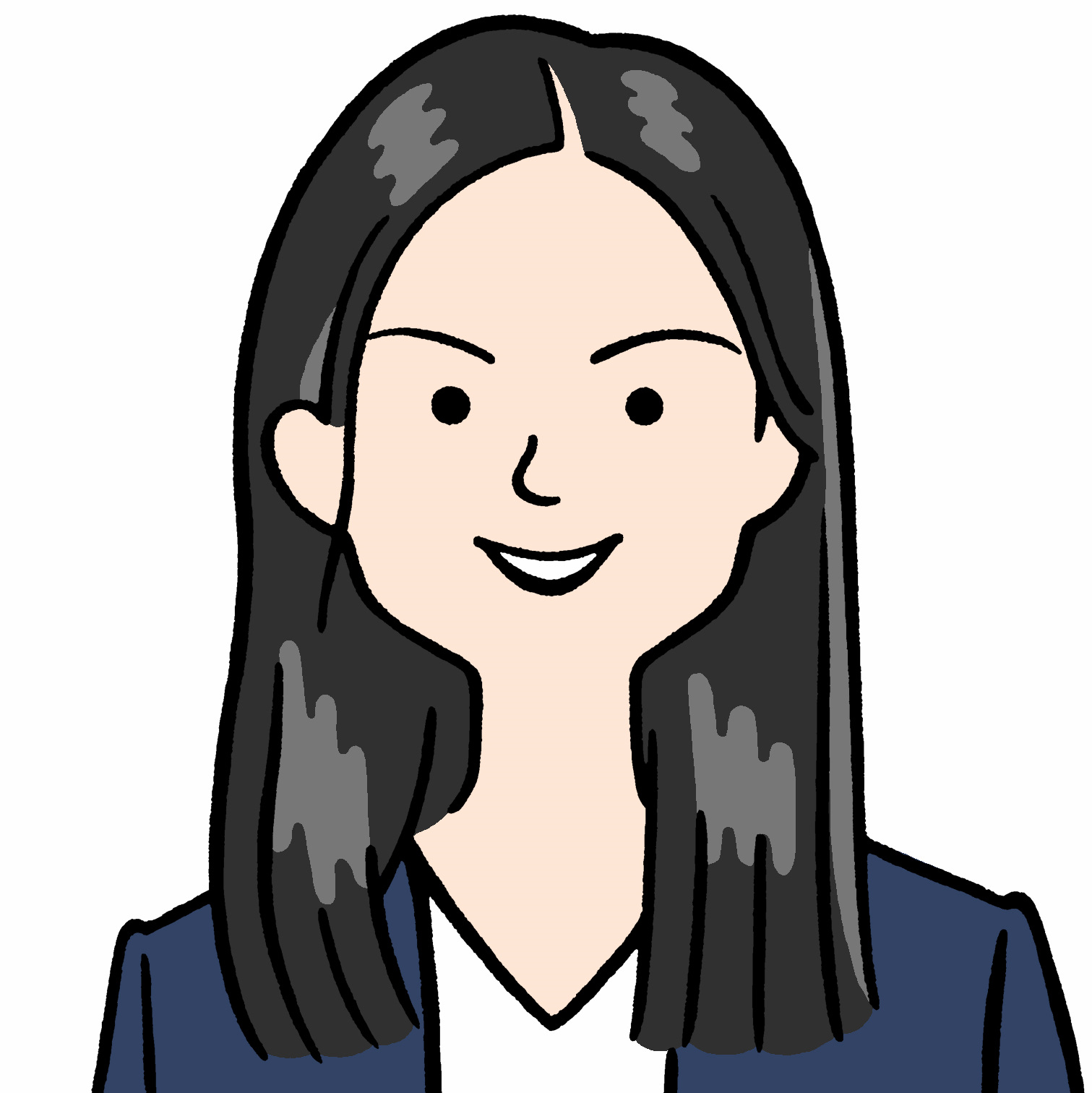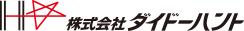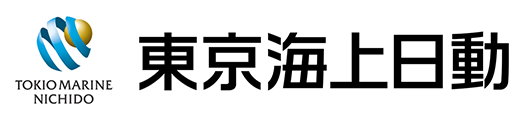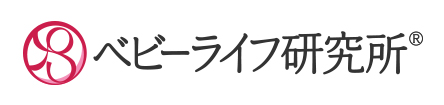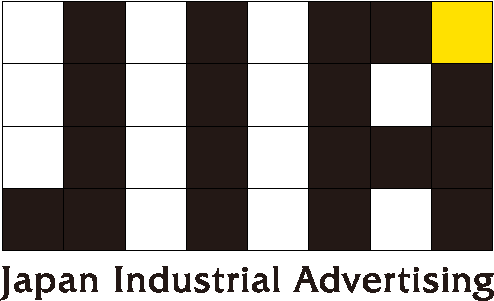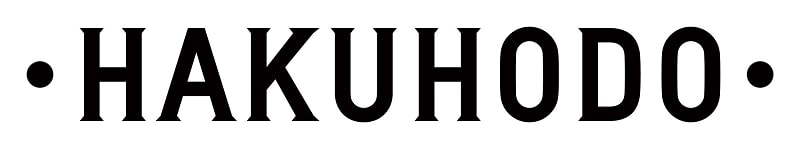ワンモア・ベイビー・ラボ
【私が経験した二人目の壁】[後編]DINKS希望だった私が2人目を欲しくなったわけ〜重度の悪阻を経て第一子出産後、「もう1人」という気持ちが芽生えたものの…〜
 秋山 開
2025年03月26日
秋山 開
2025年03月26日

本当は2人以上の子どもが欲しいにもかかわらず、その実現を躊躇する「二人目の壁」。1more Baby応援団が全国の子育て世代の約3000人に対して行った調査では、7割以上の方がこの「二人目の壁」を感じていると回答しています。
この記事では、そんな「二人目の壁」を実際に感じている方、感じたことがある方に行ったインタビューの内容をご紹介しています。もしかしたら、あなたの「二人目の壁」を乗り越えるためのヒントが見つかるかもしれません。
今回ご紹介するのは、「つわりさえなければ、もう1人を産んでもいいのに……」と語る目黒ナツキさん(43歳・仮名)とヨシヒデさん(39歳・仮名)夫妻です。前編では、お二人の出会いから、DINKS希望だった夫の心変わりから始まった1年半・600万円に及ぶ不妊治療によって妊娠するまでを紹介しました。
後編となる本稿では、2ヶ月の及ぶ重症妊娠悪阻を経ての第一子の出産や、第一子を育てるなかで芽生えた第二子への思い、そして夫婦間での温度差について聞いていきます。
「飲みものすら受け付けない」2ヶ月に及んだ重症妊娠悪阻による入院生活
1年半の不妊治療を経て妊娠したナツキさん。しかし、9回の採卵と3度の移植に関して、「もちろん大変だったけれど、自分はそこまで大きな負担は感じなかった」と語ります。そこには理由がありました。相対的に妊娠後のほうに不安があったからです。
「治療はやっと終わった。でもこのあと一番嫌なつわりがくると思うと、気持ち的に本当にうんざりでした。予想通り、このときも早いタイミングでつわりがやってきて、7週目からは飲み物すら受け付けない重症妊娠悪阻ということで、2ヶ月の入院を強いられました」
具体的にはどういった症状だったのでしょうか。ナツキさんは、そのとき次のように振り返ります。
「つわりが始まってほどなくして、食べものも飲みものも全部吐き戻してしまう状態になりました。もう100%です。体から全部の水分を出し切っちゃうような状態で、何とかぎりぎり病院へ移動して、ついたら車椅子で病棟に入ってそのまま入院。すぐさま点滴という感じでした。水分が取れないので、24時間ずっと点滴を打っていました」
入院した当初は寝たきり状態が続きましたが、点滴を打ち続けて2〜3日するとトイレやシャワーのために歩けるように。それからは、朝昼晩と出てくる病院食を食べられるだけ食べるように医者から推奨されましたが、できる範囲で食べたり飲んだりしてもすべて出てしまうという状態が続いたそうです。
「16週あたりでようやくぎりぎり吐かずに耐えられるところまでいって、なんとか退院することができました。でも気持ち悪さ自体は結局出産するまで続きました」
妊娠中の仕事はどうだったのでしょうか。
「入院中はお休みさせていただきましたが退院後は在宅勤務で産休に入るまで仕事を続けました。といっても、当時はコロナ禍で在宅勤務が多かったのでそこまでほかの人たちと働き方に差があったわけではありません。ちょうど大きな仕事から外れていたタイミングだったのも、運が良かったのかもしれません」
ヨシヒデさんも、ナツキさんと同様にコロナ禍での在宅勤務が推奨されていました。具体的には週1回程度の出社で済んでおり、ヨシヒデさんは退院後のナツキさんを全面的にサポートできたようです。
「もともと家事全般ができる人で日常生活での家事負担は半分半分、手の空いているほうがやるスタイルだったのですが、私が妊娠中はほとんど彼が担っていたと思います。あと、彼は早い段階で会社のほうに妊娠やつわりの状況を伝えていたみたいで、それもあっていろいろと配慮してくれていたと言っていました」
無痛分娩に産後ケアセンター、育児休暇制度……頼れるものにはとことん頼った
無痛分娩を選んだナツキさん。産後のトラブルこそあったものの、出産自体はうまくいきました。
「『ようやく自分だけで抱えなければいけないことが終わった』と思いました。これからは自分だけじゃない、だれにでも頼れるなと安堵の気持ちです。実際、夫は半年以上の長期育児休暇を取得してくれましたし、産後は産後ケアセンターに数週間ほど滞在する予約を入れていました」
産後ケアセンターを使いたいと思ったのは、首の据わっていない赤ちゃんを抱くのが怖くて嫌だったからだとナツキさん。
「慣れてきたら自分でやればいいから、最初はサポートしてもらおうと思ったんです。実際、出産した病院での入院中も多くの時間を看護師さんたちに見てもらっていて。なので産後ケアセンターを選ぶ基準も、『希望通りに預かってもらえるところ』でしたね」
ヨシヒデさんは7ヶ月の育休後に復帰。ナツキさんも8ヶ月の育休後に復帰をしました。復帰を決めた理由は何だったのでしょうか。
「保育園に預けられることが決まったことに加え、育休手当の減額のタイミングが迫っていたことも理由です。育児休暇の給付金は一定額以上の給料だと満額から下げられてしまいますよね。ちょっとその減額が少なくなかったので、50%になるタイミングでそれなら働いたほうがいいなと判断したんです」
そうした判断には、ナツキさんが働く会社独自の制度も影響しているそうです。
「子どもが1歳になるまでは時短勤務でも給料が保障される制度があって、それを使いたいと人事に相談し、子どもが1歳になるまで6時間勤務で働かせてもらうことにしました。それを助走として、子どもが1歳になったらフルタイム勤務で働こうと考えています」

人並みに子どもを可愛がれるようになり、「もう1人」という気持ちも芽生えたけれど
実際に出産を経て、赤ちゃん(子ども)に対する気持ちには変化があったのでしょうか。ナツキさんはこう語ります。
「私はもともと子どもに対する気持ちが低すぎたので、人並みになったかなというレベル感ですけど、考え方はやっぱり変わりました。自分の子どもを見てかわいいと感じますし、夜中や朝早くに起こされたりすることも多いんですけど、子どもに合わせて、ちゃんと自己犠牲をともなった生活ができるんだなと、我ながら感心しています」
そうしたなかで、第一子のために、「もう1人をつくってあげてもいいんじゃないか」と思うこともときどきあるのだといいます。
「経済的には困っていないので、お金の面でのハードルはありません。染色体異常のない凍結胚が残っているという面で、産むまでの時間も少なくて済みます。一度凍結の延長もしていて、お腹の中に戻してあげたいという気持ちもあります。ただ、いかんせん私の場合は妊娠期間のつわりがひどすぎるので、子どもを育てながら妊娠期間を乗り切るのは現実的ではないと諦めている感じです。」
「もう1人」への気持ちが〝実行〟に至らないのには、ほかにもあるようです。ヨシヒデさんの気持ちです。
「子どもが生まれた瞬間、もう少し喜ぶかなと思っていたのですが『こんなもんなのか』と少し驚いた記憶があります。もちろん戸惑っていただけかもしれないし、普段からあまり感情を表に出さないタイプだからということもあるんでしょうけど……。子育てには協力的で、彼なりに可愛がっているので少し安堵していますが、でもどうやら2人目はまったく興味がないみたいです。私がつわりでつらくなることを知っているからなのかもしれませんが、それでもまったく欲しいとは言いませんね」
では、ナツキさんはなぜ「2人目をつくってもいいかも」という気持ちへ変化したのでしょうか。第一子のためとは具体的にはどういうことなのでしょうか。
「私たちは高齢出産ということと、従兄弟もいないような状況なので、数十年後にはおそらくこの子は1人になってしまう。それはちょっと可愛そうかなと思いました。なので『この子のために私が頑張ったほうがいいのかな』という考えが浮かぶ一方、私自身が『もう一人欲しい』と強く思わないとやっぱりあの辛いつわりに耐えられないから無理かなというところで落ち着いた感じです」
最後に、ナツキさんはこうも語ります。
「倫理的な問題はもちろんありますが、日本でも代理出産の方法があれば前向きに検討していると思います。それくらい私の場合はつわりがひどかった。健康で妊娠・出産に負担を感じない人が代理出産で対価をもらい、妊娠が難しい人、困難な人がお願いしますといってお金をお支払いするという、お互いにウィン・ウィンな関係になるのであれば、私は個人的に『いいんじゃないかな』と思っています。もちろん、つわりがなくなる方法があれば一番いいんですけどね。妊婦が飲める薬は限られるので難しいのはわかっていますが。」
今回は、妊娠・出産や子どもに対する気持ちが変化していった目黒さん夫婦のお話でした。ナツキさんの壮絶なつわり体験は、ご本人にしか理解しえないものなのかもしれません。しかし、そうした経験を自分や身近な人、あるいは会社の同僚がする(している)のかもしれないということを頭の片隅に入れているだけでも、社会は少し良いほうに変わっていくのでないでしょうか。目黒さん、貴重なお話をありがとうございました。
関連記事
ランキング
カテゴリー
アーカイブ
-
2026年