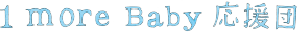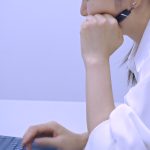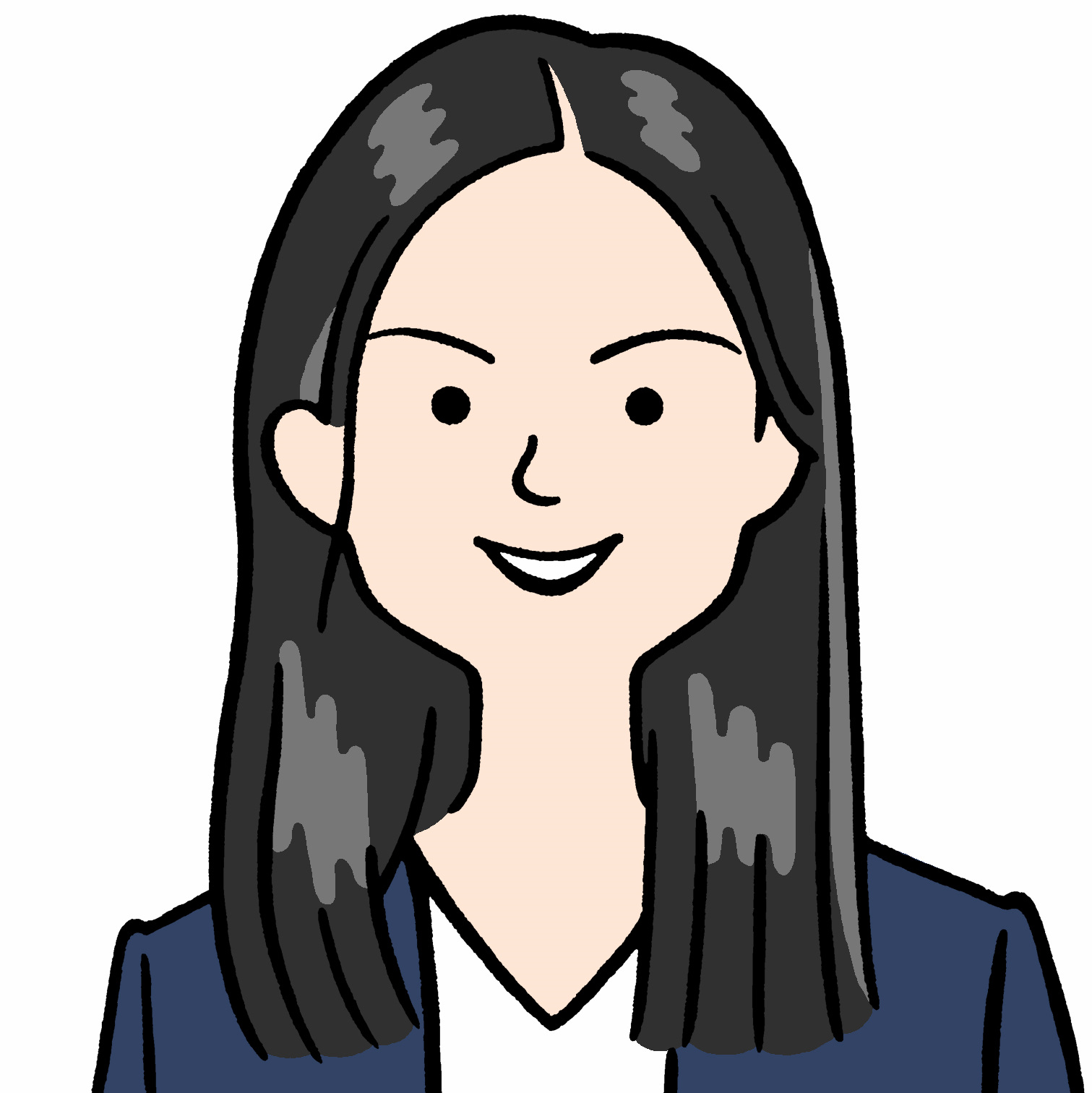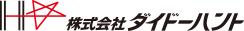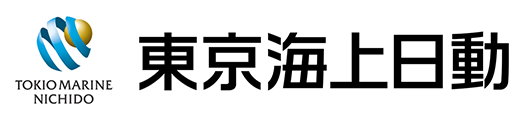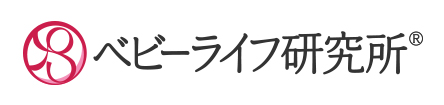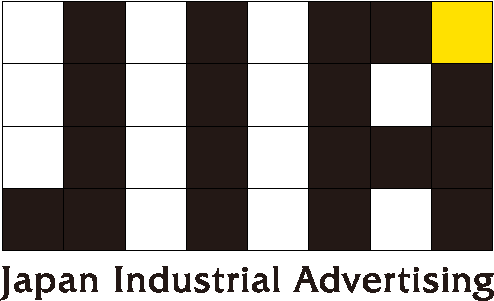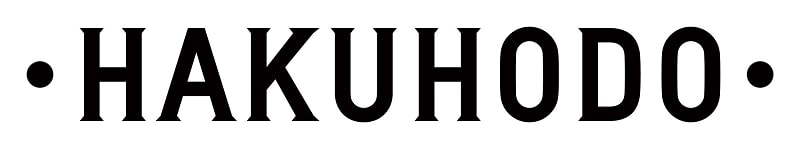ワンモア・ベイビー・ラボ
【パパ育休の実態と本音】コンサル会社勤務のパパが提案する戦略的「育休」=後編=
 秋山 開
2025年11月18日
秋山 開
2025年11月18日

「男女の仕事と育児の両立支援」を目的に、父親が育児休業を取得するための制度が整ってきています。厚生労働省によれば令和6年度の〝パパ育休〟取得率は過去最高の40.5%に達しました。
実は、夫の家事育児の時間が長くなるほどに、第二子の出産率が高くなる*こともわかっており、パパ育休は日本が抱えている出生率の低下や人口減少に対する1つの対策としても注目を浴びています。
しかし、企業や地域ごとに温度差があるのも確か。まだまだパパ育休取得へのハードルは残っています。そこで本連載では、実際にパパ育休を取得した家族へのインタビューを実施し、その実態や本音について迫ります。
育休を取るか悩むかた、うちの会社で取れるはずがないと考えているかた、子育て世代の部下をもつかたなどへのヒントとなれば幸いです。
(*厚生労働省「第14回21世紀成年者縦断調査(2002年成年者)の概況」)

【プロフィール】
夫:大森 竜也(30歳/仮名)
コンサルティング会社 勤務
妻:大森 真由子(31歳/仮名)
総合電機メーカー 勤務
子:2人(2021年2月生まれの4歳と2024年3月生まれの1歳)
お住まい:東京都(23区内)
【産休・育休期間】
夫(第一子)2021年2月~2022年4月
(第二子)2024年3月~2025年4月
妻(第一子)2020年12月~2021年10月
(第二子)2024年1月~2024年7月&2024年11月〜2025年4月
-取材日:2025年7月某日
経験値によって余裕が生まれ、第一子にも寛容になれた2回目の育休
前編でも記したように、大森さん夫婦は第二子の育休期間中、第一子を保育園に預けていました。それは希望してのことだと語ります。
「保育園で学べることは多いと思っているので、下の子の育休中に自宅で上の子もみるということは考えませんでした。自治体によっては『育休退園』というルールがあると認識していたので、事前に私たちが住んでいる自治体に、それがないことは確認しておきました」
1人目のときと比べ、さまざまな面で余裕ができた2人目の育休のときは、特に「良かった」と感じたこともあると竜也さんは言います。
「ひとつは、2人目の育休のときは家族の時間がすごく長く取れたのが良かったです。子ども2人の成長を家族みんなで見守れたことはもちろん、夫婦間の会話もすごくたくさんできました。2人で協力して子育てをしていますし、2回目の子育てという経験値も上がっていたので余裕がありました。だから、上の子に対しても寛容になれるというか、少しくらいのわがままだったら、うまくいなしながら楽しく過ごすということもできました」
1人目のときにはできなかった家族旅行もできました。関西、沖縄、北陸そして韓国などに足を運んだそうです。
「関西と韓国は友人の結婚式が理由でしたが、沖縄は私と妻の両方の希望です。雪遊びと恐竜博物館が目当てだった北陸は、上の子の希望でした。とにかく、家族の時間がじっくりと取れたことは、非常に良かったと思っています。また、夫婦ともに育休取得中だったため、フレキシブルに日程調整ができ、宿泊費が安く、空いている時期を狙って旅行ができたこともありがたかったです」
家庭を持ち、育休を経て生じた「価値観」の変化
育休を取得する前と後で、どのような変化があったのでしょうか。竜也さんは「仕事へのやる気が下がったわけではない」としたうえで、次のように言います。
「子どもが生まれる前は、やっぱり仕事が生活の中で最も大きな比重を占めていました。具体的には、仕事でいかに評価してもらうか、自分のやりたいことを実現できるかを考えていました。でも、家庭をもつことで、私のなかでは家庭の優先順位が上がりました。もう少し詳しくいえば、子どもができたり、子育てをしていくなかで、そうした気持ちが増していったと感じています。もちろん仕事では評価されたいですが、無理をしない範囲でそれを成し遂げ、家族の時間もきちんと確保して、過ごしていきたい。そこはだいぶ変わったかなと思います」
さらに、育休の取得に対する考え方にも変化があったようです。
「もともと私は、『育休は取りたい人が取ればいい』と思っていました。でも、私の妻が子どもをもつ同僚や友人と話をするときには、だいたいいつも『うちの夫は育休が取れなかった』『竜也さんの勤め先は良い会社だね』みたいなことを言われるらしいんです。
それを聞いて私は『取りたくても取れない人もいるのか。雇用保険に入っている会社に勤めていたら、育休は法定の権利。自営業の方とかでない限り、誰でも取ろうとすれば取れるはず。育休の取得を言い出しづらい環境があるのならば、変えていくべき』と思うようになりました」
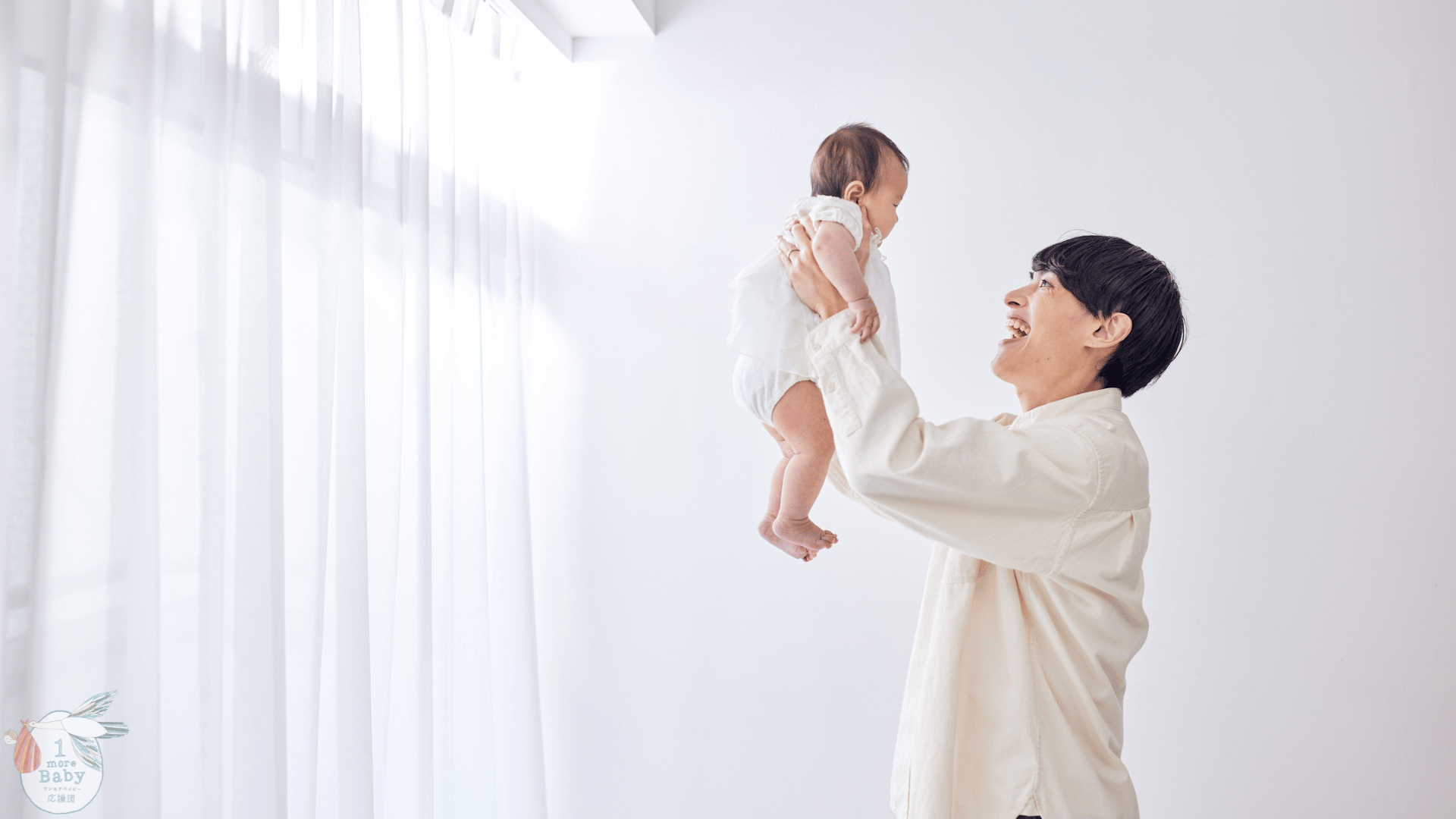
夫婦そろって円滑に復職できた理由とパパがワンオペをこなすコツ
社内チームの協力もあって、スムーズに職場復帰できたようにみえる竜也さん。育休中に上司や同僚との交流はあったのでしょうか。
「実はほとんどなかったです。上司が数ヶ月に1回くらい、メールやLINEなどで連絡をくれる程度でした。その内容自体も、最近の社内の様子をアップデートしてくれたり、『育休の予定に変わりはありませんか』という確認であったりと、割とフランクなやりとりしかありませんでした」
スムーズな職場復帰のために工夫したことは、ほかにあるのだと竜也さんは話します。
「特に第二子の復帰の際には、第一子のときの経験があったので、『子どもが病気のときは、保育園から呼び出しがくることがある』ということを事前に上司に伝えました。ただ、チームのなかには私以外にも小さい子どもがいる人もいたので、上司はもうそのあたりは把握していて、想定の範囲内という感じでした」
さらに、働く時間帯についても上司に伝えていることがあります。
「私の定時は9時半〜17時半なんですけど、『保育園の送り迎えの時間にあわせて9時〜17時にずらして勤務する』ということだったり、仮に残業する場合は『子どもを寝かしつけた後の◯時から◯時までやります』ということなどを伝えるようにしています。上司や同僚の理解もあって、幸運なことにいまのところ大きなトラブルはなく、職場復帰を果たせていますね」
スムーズな職場復帰は、妻である真由子さんも「できた」のだとか。夫婦そろって育休からスムーズに復帰できた理由は、育休期間中に、2人とも同じように育児と家事ができるスキルを身につけたからだと竜也さんは考えています。
「2人で同時に育休を取ったのは、非常に大きな経験となっていると思います。私も妻も、ひとりで家事育児を回せる戦力をもつことができましたから。たとえば子どもが病気で保育園から電話がかかってきたとき、私でも妻でも、どちらでも対応できます。保育園の送り迎えも、どちらか一方が繁忙期に入っていたら忙しくないほうが行けばいい、みたいな」
さらに、ワンオペを実施するにあたってのコツを伝え合うこともあります。
「私はワンオペをこなすためには、完璧を目指さないことが大事だと思っています。慌てず、怒らず、できないことは諦める。そうすると、かなりラクになります。できなかったことは、ワンオペではなくなったタイミングで後からやればいいですからね。『お互いワンオペのときは無理しないようにしようね』と夫婦で話し合っています」
家族の絆を深め、人生を豊かにしてくれた育休
そのスキルは子育てが終わるまでずっと活かし続けられると竜也さんは感じているようです。だからこそ、周囲にいる男性陣には、できるかぎり育休を勧めるようにしているのだと語ります。
「もうすぐ子どもが生まれる予定の男性に相談された際は、授乳以外の育児や家事は全部できるようになっておいたほうがいいし、絶対にあとになって『あのときできるようになってよかった』と思うよと伝えています。受け身にならずに、主体的にやっていくにはスタートダッシュが肝心ということも言います。特に1人目の新生児期。そこで関われるかどうかがカギだから、そのためには絶対に育休を取ったほうがいい、とアドバイスしています。もちろん、相手に合わせてもっとマイルドな言い方を選んでいますけど(笑)」
最後に、育休の取得を検討しているパパやママに向けてのメッセージを聞くと、竜也さんはこのように語ってくれました。
「育休を取ることで家族の絆が深まったと感じていますし、初めて歩く瞬間とか子どもの成長を間近で見られたことも含め、人生の幸せな時間が増えました。育休を言い出しづらい環境もあるかとは思いますが、少しでも取りたい気持ちがあるならば、まずは周囲に相談して前向きに検討してほしいなと思っています。もちろん仕事を優先したいパパ・ママももちろんいて、それはそれでアリだと思いますが、私は育休を取って本当に良かったと思っています」
関連記事
ランキング
カテゴリー
アーカイブ
-
2026年