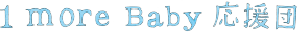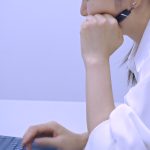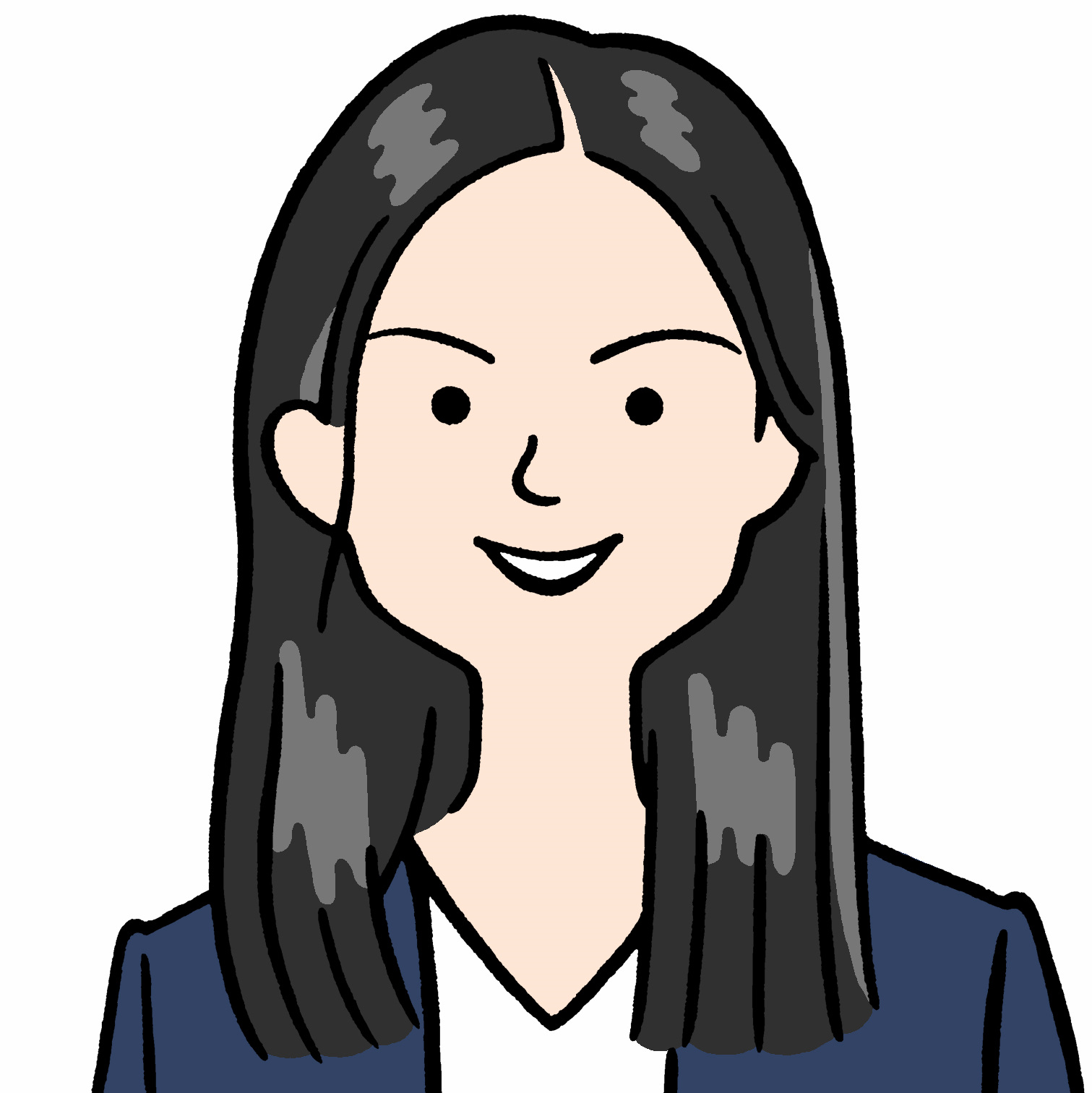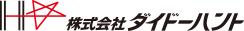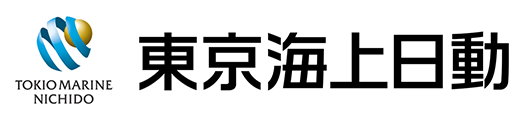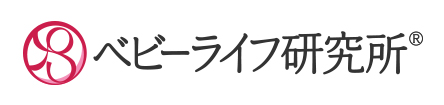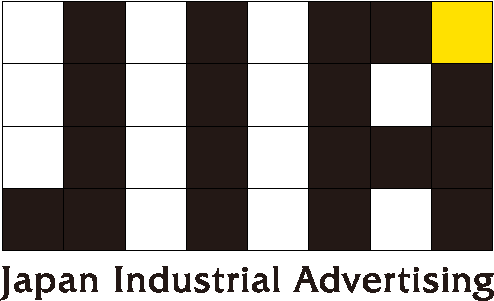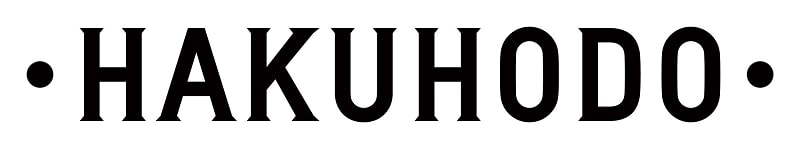ワンモア・ベイビー・ラボ
「子どもよりパートナーとの関係性に注力するべき」と語るワケ/オランダ・インタビュー vol.8
 秋山 開
2025年11月07日
秋山 開
2025年11月07日

「世界一子どもが幸せな国」といわれるオランダ。これはユニセフのリポートによるものです。さらにオックスフォード大学ウェルビーイング研究所が主導するWorld Happiness Report(世界幸福度報告)の2025年版でも、オランダは第5位に入っています。ちなみに、日本は同ランキングで55位です。
1more Baby応援団では、このように幸福度が高いオランダの社会や暮らしを探るべく、2016年より定期的な調査を行っています。その調査内容は、『18時に帰る』という書籍として1冊にまとめたほか、インタビュー記事等をこちらの「ワンモア・ベイビー・ラボ」でも掲載してきました。
Vol.7~10では現地在住者の協力のもと、オンラインを通じて2つの子育て家庭に伺ったお話をご紹介していきたいと思います。
============
vol.7とvol.8ではフェレンスさん(48歳)とジョシンさん(41歳)夫婦を紹介します。人口約15万人の街(アーネム)の郊外に居を構えるお二人は、8歳、6歳、3歳のお子さんをお持ちです。建築業界でエンジニアや設計士として働いてきた夫のフェレンスさんは、現在、主夫をしています。一方、妻のジョシンさんは、眼科医として専門病院で働いています。
「オランダに専業主夫は多くない」と話すフェレンスさん、そして「子どもももちろん大切だけれど、それ以上にパートナーへのコミットメントが不可欠」と語るジョシンさんに、オランダでの子育てについてインタビューしました。
後編となるvol.8では、お二人が「子どもとの関係性以上に、夫婦関係を重要視している理由」や、フェレンスさんが働くオランダの医療業界に起きている変化などについて聞いていきます。
シングル家庭や母親が2人いる家庭など、子どもたちはいろんな形の家族を知っている
─夫婦の役割分担について、お子さんたちに話をしたり、なにか聞かれたりした経験はありますか?
「まったくありません。彼らにとって、私たち夫婦のスタイルは自然なもの。ほかを知らないので、比べようもないでしょうし、質問をしてきたこともないです。彼らの学校の友だちのなかには、シングルマザーやシングルファザーもいるし、お母さんが2人いる家庭だっています。いろいろな形の家族を知っているので、他人や自分たちの生き方に関して疑問に思うことはないんだと思います」(ジョシン)
─そうしたオランダの価値観というのは、いつ頃からあるのでしょうか。
「私たちの生き方は、私たちの前の世代、要は親の世代が可能にさせてくれたものだと思っています。彼らが十分にオープンマインドで、価値観を変えることに積極的だった。だからこそ、いまのオランダは多様な生き方が認められる社会になっているのだと感じます」(ジョシン)
─お二人が育った家庭、つまりご両親はどういう働き方や生き方だったんでしょうか。
「実際のところ、僕もジョシンも、お父さんが週5で働き、母親が家にいるという伝統的な家庭で育ちました。僕の場合は、末っ子が12歳になったときに母親は仕事に復帰し、ジョシンの母親は彼女が8歳になったときに、小学校の先生として仕事を再開しましたが。そういう意味では、子どもが帰ってきたときに(親である)僕が家にいるというスタイルを取っているのは、家に帰ったら誰かがいるという温かさを経験したからなのかもしれません」(フェレンス)
─どちらが良いとか悪いとかではなく、多様な生き方や働き方が認められる社会になっているということだと思いますが、前の世代で起こったことをもう少し具体的に教えてください。
「オランダでは1970年代から1980年代で大きな変化がありました。特に1980年代には両親ともに働かないと家賃や食費が払えないというような、経済的な状況がありました。それ以前だと、どのような職業であっても父親が働けば、母親が働かなくとも十分に生きていくことができた。家族を養えた。でも、1980年代からそれが難しくなって、共働きに移行し、いまに至っています」(フェレンス)
「そうした意味では、私たち夫婦のスタイルはどちらかというと珍しいほう。金銭的にとても余裕があるというわけではありませんが、生活の豊かさを十分に感じています」(ジョシン)

夫婦の関係性を大事にできれば、自ずと子どもたちは安心して育つ
─事前アンケートのなかで、「幸せな家庭を築くには、子どもよりも、まずはパートナーとの関係性に注力するべき」ということを書いてくださいました。これについても詳しく教えて下さい。
「子どもが生まれると、それぞれが父親と母親という新しい役割が与えられます。でも、忘れてはいけないのは、なぜ子どもが生まれたのか。夫婦が愛し合っていたから子どもが生まれてきたわけなので、まずは夫婦の関係性を大事にしておかないといけないと思っています。逆に言うと、パートナーのことを大事にしていたら、自然と子どもたちも安心して、自由にのびのびと育つことができるのではないでしょうか」
「子どもというのは、両親が一緒にいてほしいと願うものです。もしも私たちが夫婦の関係性を大切にせず、別々の生活を始めてしまうと、子どもたちは両親の気を引こうと様々なトラブルを起こしていくでしょう。夫婦の関係性が大事にされていれば、子どもたちはそのことに気を使う必要がなくなる。だから私たち2人は、子どもとの関係以上に、夫婦関係を大事にしているということです。子どもになにかトラブルが起きたら、親を見れば原因がわかると言われることがあると思いますが、その通りだと考えています」

15年前は男性医師が多かった。いまは女性医師のほうが目立つ
─最後に、ジョシンさんにお聞きしたいのは、医療業界で女性が働く難しさです。日本では医学部に入る女子学生を減らすような措置をしていたことが問題になったことがありました。要は、女性医師は出産や子育てがあって医者のようなハードな仕事は難しいから、大学入試の段階でハードルを上げておくというのが、背景の1つとしてあったようです。オランダではどうなのでしょうか?
「オランダの医学部は8割が女性です。女性のほうが入りやすいわけではなく、女性のほうが医学部に入るモチベーションが高いからだと言われています。実は、私が仕事を始めた15年ほど前は男性医師のほうが多かったように思います。でも、ガラッとそれは変わりました。たとえば私がいま所属しているチームは10人ですが、そのうち男性は1人だけです。近年はフルタイムで働いていた男性医師の定年退職が続いていますので、どんどん女性が増えています。また、ほかの業界と同じですが、ヘルスケアの部門でも、女性と男性とに関係なく、パートタイム勤務が主流になってきています」
─ありがとうございます。そうした変化によってどのような影響が出ていますか? あるいは出ていませんか?
「昔は、1人の患者に1人の医者というように、担当が決まっている傾向にありました。1対1の関係性のなかで信頼が生まれ、治療が進んでいったとも言えます。でも、いまは変わっています。1人の医者の勤務時間は短くなり、休みも増えました。今日は◯◯医師はいないので、代わりに私が診ますということが、当たり前になっている。1人の患者を複数の医者が診るということです。やはり、そのなかで治療のやり方も変えていかないといけない。ですからオランダでは、どんどん新しいやり方を試していますし、どんどん変わってきています」
関連記事
ランキング
カテゴリー
アーカイブ
-
2026年