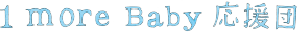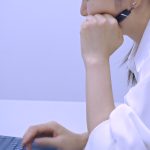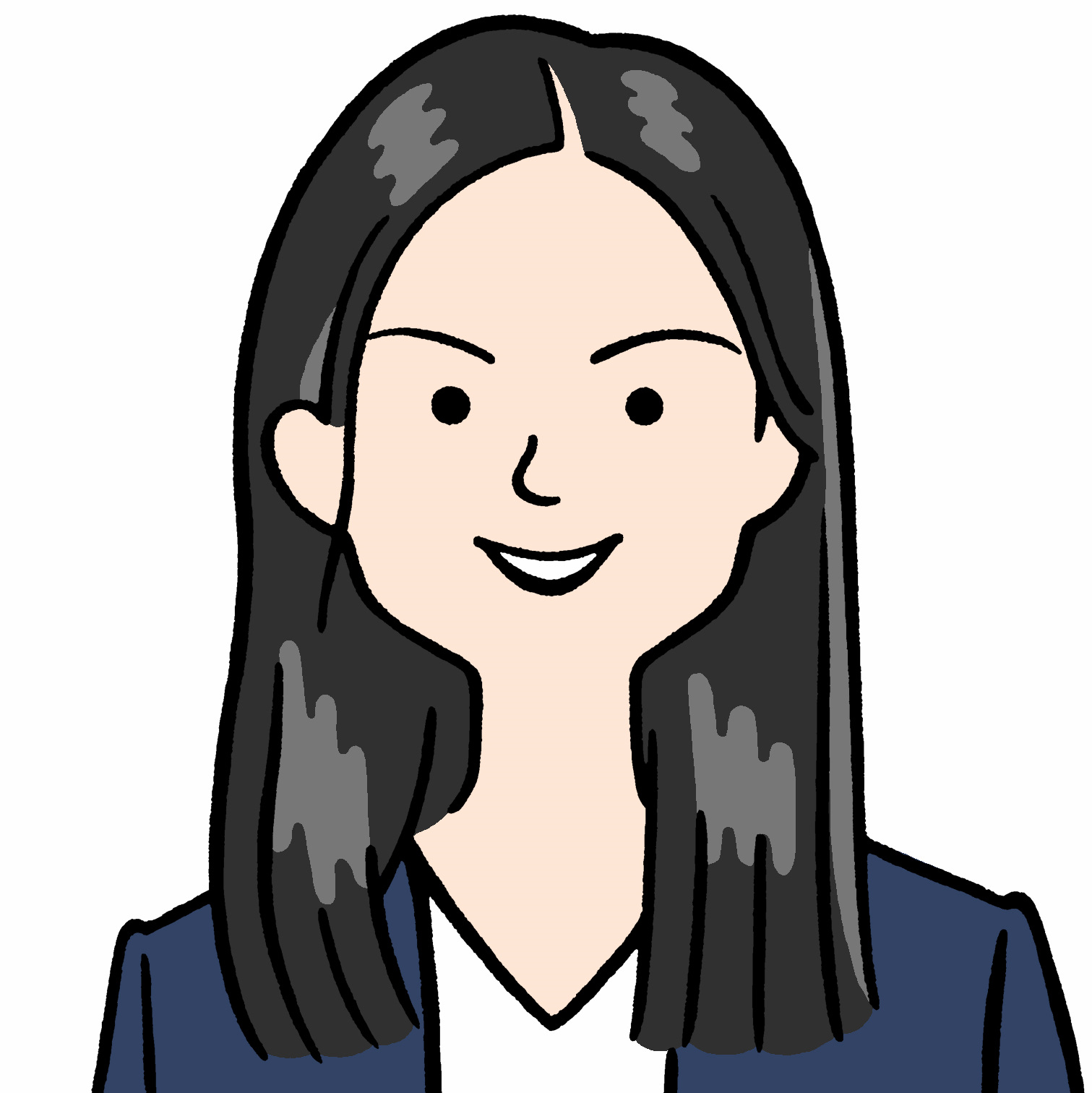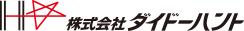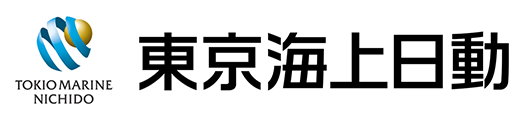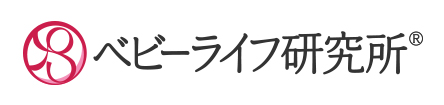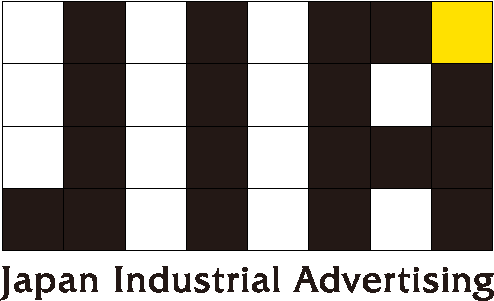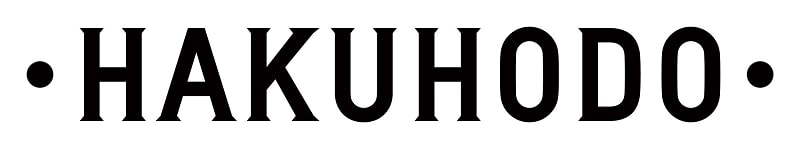ワンモア・ベイビー・ラボ
【パパ育休の実態と本音】コンサル会社勤務のパパが提案する戦略的「育休」=前編=
 秋山 開
2025年10月21日
秋山 開
2025年10月21日

「男女の仕事と育児の両立支援」を目的に、父親が育児休業を取得するための制度が整ってきています。厚生労働省によれば令和6年度の〝パパ育休〟取得率は過去最高の40.5%に達しました。
実は、夫の家事育児の時間が長くなるほどに、第二子の出産率が高くなる*こともわかっており、パパ育休は日本が抱えている出生率の低下や人口減少に対する1つの対策としても注目を浴びています。
しかし、企業や地域ごとに温度差があるのも確か。まだまだパパ育休取得へのハードルは残っています。そこで本連載では、実際にパパ育休を取得した家族へのインタビューを実施し、その実態や本音について迫ります。
育休を取るか悩むかた、うちの会社で取れるはずがないと考えているかた、子育て世代の部下をもつかたなどへのヒントとなれば幸いです。
(*厚生労働省「第14回21世紀成年者縦断調査(2002年成年者)の概況」)

【プロフィール】
夫:大森 竜也(30歳/仮名)
コンサルティング会社 勤務
妻:大森 真由子(31歳/仮名)
総合電機メーカー 勤務
子:2人(2021年2月生まれの4歳と2024年3月生まれの1歳)
お住まい:東京都(23区内)
【産休・育休期間】
夫(第一子)2021年2月~2022年4月
(第二子)2024年3月~2025年4月
妻(第一子)2020年12月~2021年10月
(第二子)2024年1月~2024年7月&2024年11月〜2025年4月
-取材日:2025年7月某日
「育休は取っていいんだ」。気づきをくれた同期
本稿で紹介するのは、大森竜也さん(仮名)、真由子さん(仮名)夫婦です。お2人には、4歳と1歳になるお子さんがいますが、どちらのときにも竜也さんは、育休を取得しています。そもそもなぜ竜也さんは、育休を取ろうと考えたのでしょうか。
「私は1度、転職を経験しているのですが、新卒で入った最初の会社のときに、2年という長い育休を取っている同期がいたんです。すごく仲が良かった彼の話を聞いたときが、『男性でも育休を取っていいんだ』と思ったきっかけでした」
そのときはまだ社会人3年目。20代半ばという年齢でした。
「最初は『早い』と思いました。だから今後のキャリアとかの心配はしていないのかとか、実際に取ってみてどうなのかとか聞きました。『すごく充実している』と言っていて、育休は変に心配しなくとも、取っていいんだなと感じました。結局、私自身はその会社ではなく、転職した次の会社で育休を取ることになるんですけど」
コンサル業界といえば、一般的には激務のイメージがありますが、仕事に支障はなかったのでしょうか。「まだ管理職側ではなかったから、育休は取りやすい立場にあったと思う」と前置きをしたうえで、こう話します。
「管理職のひとつまえのポジションでしたし、仕事がプロジェクトベースで進んでいたので、担当しているプロジェクトの区切りをうまく調整できたら、人員的には問題はありませんでした」
日頃の仕事への取り組み姿勢が「上司や同僚の理解」につながる
さらに竜也さんは続けます。
「常日頃からチームに貢献できるよう努力していましたし、妻が安定期に入った段階で上司に相談し、『育休を取るつもりだ』ということは伝えていました。それが功を奏したのかどうかは明確ではありませんが、少なくともチームのみんなはとてもよく理解してくれましたし、すごく協力的だったと思います。当時はコロナ禍でリモートワークがメインになっていたことも、後押ししていたかもしれませんが……」
育休取得にあたって仕事上のハードルはなかったようですが、それ以外の金銭面での不安や、妻である真由子さんを含めた家族と同僚の反応などはどうだったのでしょうか。
「育児休業給付金制度などで基本的にはやりくりできると考えていました。あとは貯金もありましたし、万が一、金銭的に困ったら私の父が『いつでも援助できるから』と言ってくれていたので、安心感がありました。実際には、多少の貯金の切り崩しがあった程度で済みました」
ちなみに育児休業給付金は180日までが休業開始時賃金の67%、それ以降は最長2年まで50%が出ます。休業開始時賃金は、具体的には休業開始日前直近の6ヵ月間に支払われた賃金総額を180で割った額となります。
周囲の反応はどうだったのでしょうか。妻の真由子さんやご両親は、竜也さんと同様に、不安を感じている様子はなかったようです。
「妻も(育休を)取ってくれたら嬉しいと、すごく前向きでした。うちの親も、妻の親も、みんなすごくポジティブな反応で、『いいじゃん、いいじゃん』と言ってくれていました」
ポジティブな反応は同僚も同じだったようです。
「先ほども言ったように、妻が安定期に入ったあとくらいから、上司に育休を取るつもりだと伝えたのですが、その段階からすでに『育休を取るという前提で、いまから準備と調整を進めます』と受け入れてくれて、上司も同僚も『いいじゃん、好きなだけ取っていいと思うよ』とか、『自分も取ろうかな』といった反応でした」

子育てと仕事を両立させるための情報収集と職場での環境づくり
育児休業に関する制度は、「第一子のときは初めてだったので、特によく調べました」と竜也さん。こう続けます。
「基本的な情報はインターネットで調べました。会社独自の制度に関しては、社内サイトに特設ページがあって、そこでまとめられているので助かりました。法定だと、育児休業は最長で2年までですけど、会社規定で3年まで取れることなどが書いてありました。3年目は給付金がありませんが、復職を希望するけれど保育園に入れなかった場合などで、育休を延長しても復職の道があるので、ぜひ検討してくださいと書いてあったと思います。あとは、ベビーシッター利用の補助制度もありましたね」
会社からのサポートという意味では、希望する人事異動を叶えてくれたこともあったようです。
「第一子を保育園に預けて復職したら、子どもがすごく頻繁に風邪を引きまして、その当時はクライアントワークでしたので、どうしても休めなかったり、残業時間が長くなりがちでした」
子どもがいなかったときに比べれば、チームで配慮してもらえていた分、労働時間は減っていたと言いますが……。
「私には、『18時の保育園のお迎えから寝かしつけまでは、仕事をせずに家族で過ごす』という理想がありましたので、子どもの生活リズムに合わせた結果、残業時間は短くなっていても、働く時間が深夜や早朝になってしまって、働き方が辛くなっていきました」
そこで、竜也さんは労働時間が読みやすく、残業も少ない人事部への異動を希望しました。子育てと仕事をうまく両立できるよう、会社はその希望を受け入れてくれたのだと言います。
妻の早期職場復帰のため「二度のワンオペ育児」を経験
2月生まれの第一子の保育園入園は翌々年度が始まる4月でしたが、実は、その5ヶ月前の11月に真由子さんは竜也さんよりも早く職場復帰をしています。それは第一子が生後9ヶ月のときでした。
「妻は子どもともう少し長く過ごしたい気持ちもあったようですが、仕事の関係で早めに戻りたいという話になって、11月に復帰しました。私はまだ育休期間中でしたので、結果的に『戻りたいときに戻れたのでよかった』と彼女は振り返っています」
真由子さんの復職後、竜也さんはひとりで子育てをしました。その期間は4ヶ月あまり。不安はなかったのでしょうか。竜也さんは、「コロナ禍での特殊な状況だったからかもしれませんが……」と、当時を振り返ります。
「子育ても家事も2人でまわしてきたので、1人でもまわせるだろうという自信はありました。だから1人で子育てすることに関しての不安はありませんでした。ただし、実際に子どもと2人きりになると、ストレスを感じることはありました。というのもコロナ禍ということもあって、友人を呼ぶというのも難しいし、〝子育てひろば的な場所〟も利用しづらい状況にありましたので、基本的に昼間はずっと赤ちゃんと2人きりだったからです」
第二子の育休時も、会社の繁忙期のため先に真由子さんが一時的に復職した関係で3ヶ月間のワンオペ育児期間がありました。そのときには第一子のときのようなストレスはなかったようです。
「通常時よりも2時間短い利用時間になりますが、上の子は保育園に通っていたので、日中は私と赤ちゃんの2人きり。でも、暇を見つけては子育てひろばなどに行って、ほかの子育て中のかたと話ができたので、1人目のときのようなストレスは感じませんでしたね」
一方で、子育てひろばでむず痒い思いをすることはあったようです。
「パパがそうした場所に足繁く通うことは稀だったみたいで、珍しがられて質問攻めにあうこともありました。そうしたときには、『育休を取って、1人で子どもの面倒を見ている』ことを説明するのですが、何度も同じことを聞かれるので、少し面倒な気持ちが出てきたこともありました。もちろん悪い気がするわけではないんですけど、自分としてはあたりまえのことをしているだけなので、『パパ、すごい』とか言われるたびに、むず痒くなっていました」
後編に続く
関連記事
ランキング
カテゴリー
アーカイブ
-
2026年